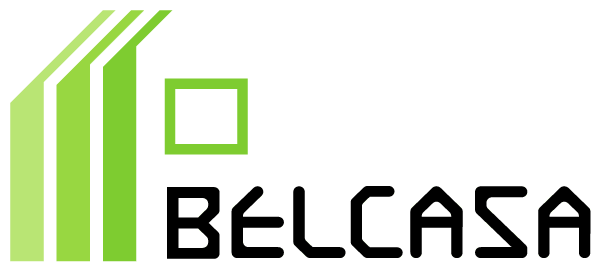フロアコーティングは市販の材料でDIYすることも可能ですが、仕上がりや耐久性、長期的なコストを考えると業者施工との違いは大きいものです。本記事ではDIYとプロ施工それぞれのメリット・デメリットを専門家が比較。床材種類、目的やライフスタイルに合わせた最適な選び方を解説します。
フロアコーティングをDIYで行うことは可能?
未経験者であっても自分でフロアコーティングを行うことは可能です。注意点もありますが、ここではDIYのやり方を紹介します。
市販のDIY用コーティング剤の種類
現在、ホームセンターやECサイトでは多種多様なコーティング剤が入手可能です。大手通販サイトの売れ筋商品には以下のものがあります。カッコ内は代表的な製品の現在価格です。
- 水性ウレタン系:滑り防止性や抗菌性のあるものまで。(1L/3,960円)
- ガラスコーティング剤:傷防止性や子供の落書き対策。(1L/39,800円※施工キット一式付属)
- 自然塗料系:蜜蝋ワックス・植物性オイルなどが主成分。(120ml・2本/1,990円)
- スプレータイプ:艶出し・撥水にガラス成分が含まれるものも。(500ml/2,999円)
- 床用ニス:油性ウレタン床用ニス、つやあり・高耐久。(0.7L/2,092円)
DIYの一般的な手順
作業の手順は、購入したコーティング剤により多少違いますが標準的には以下の流れです。
- 床面の清掃(掃除機がけ・拭き掃除)
- コーティング剤の塗布
- 乾燥
塗布する道具はコーティング剤の種類により、小型のマイクロファイバーモップ、クロス、柄のついたモップなどが推奨されています、液剤を入れるトレイなども必要です。
また、副資材としてバケツ、タオル、新聞紙、マスキングテープを準備してください。バケツ・タオルは水拭きに、新聞紙はコーティング剤のボトルを置くときに床上に敷く用、マスキングテープは塗らない部分(巾木や見切り材など)に貼るとはみ出して塗装することを防げます。
DIYで期待できる効果と限界
市販のコーティング剤には詳細なマニュアルや施工動画が用意されていることもあります。または、動画サイトなどで塗り方を勉強することも昨今では可能です。そういった意味では施工の経験がなくても、手先が器用だったり、勘どころの良い方なら最初からうまくいくこともあります。
ただし、市販のコーティング剤は専門業者の使用するものとは微妙に違いがありますし、良い材料だとしても床材とのマッチングの問題もあります。
また申し上げにくいのですが、上手に塗布できた自覚があったとしても、プロの目から見ると均一でないことがあります。厚塗り部分があると将来的に「剥がれ」「割れ」のリスクがあります。本来のコーティング剤の機能を発揮させるには、やはり経験も必要です。
とくにガラスコーティングや油性ニスは、失敗したからといって簡単にはやり直しがききません。やるなら、しっかりと事前にマニュアル等を読んで計画的に実行しましょう。
DIYフロアコーティングのメリット・デメリット

メリット・デメリットを一覧にしましたのでご参照ください。
メリット
- 初期費用を抑えられる
- 自己責任ですべて行うことができる
- 自分で補修が可能(な場合もある)
デメリット
- うまく仕上がらないことも
- 材料や技術により業者施工と比較して耐久年数が低い
- 資器材の購入費がかかる
- 自分の床と相性のよいコーティング剤を選ぶ難しさ
- 施工不良の保証がない
DIYフロアコーティングでよくある失敗例
自分でコーティングしたけれども、うまくいかず当社へ補修や再コーティングを依頼されるケースが最近増えています。原因を分析すると、以下の3つに集約されます。
DIYコーティング失敗の3大要因
- 床材と塗料の相性を考慮していない
- 塗るのが難しいコーティング剤の使用
- レビューや素人意見でコーティング剤を選ぶ
床材とコーティング剤の相性
フローリングには、シートフローリング、突板フローリング、無垢フローリングなどの種類があります。主に表面の素材「化粧板」や「仕上げ」により最適なコーティング剤が異なります。相性のよくない組合せでは、塗りムラが発生したり、剥がれたりすることがあります。市販コーティング剤だからといって、汎用性が高いということはありません。
以下に専門家の視点から相性のよいコーティング剤を紹介します。
| 床材 | 特徴 | 推奨される塗料タイプ |
|---|---|---|
| シート | 木目がプリントされたオレフィンシート | 水性ウレタン(高密着タイプ)・ガラスコーティング |
| 突板 | 薄くスライスした木材 | 水性ウレタン |
| 無垢注 | 一枚板の天然木材 | 自然塗料 |
(注)無垢はウレタン塗料等で「造膜仕上げ」されたものもありますが、ここでは「素地仕上げ」「オイル仕上げ」の製品を想定しています。造膜仕上げは性質の近い突板を参考にしてください。
シートフローリングは液剤を弾くような特性がありますので高密着仕様の水性ウレタンが無難です。またガラスコーティングは比較的、粘度が低く塗りやすいですが厚塗りは厳禁です。
突板フローリングは高濃度の水性ウレタンでコーティングすると艶感のよい保護膜が形成されます。使用歴があり消耗しているものは、ガラスでは薄膜設計のため十分な保護膜が形成されないことがあります。消耗度が高い場合は油性ニスも考えられますが、溶剤臭や失敗したときの塗膜剥がしが困難なことからおすすめはできません。
素地仕上げ・オイル仕上げの無垢床は自然塗料(オイルや植物性ワックス)でメンテナンスすることが基本です。ガラスや水性ウレタンは床材に吸収され保護膜が形成されません。ただし、専門業者なら下塗りや研磨工程などの下処理作業を行うことで保護膜を形成することが可能です。
自然塗料は浸透型(または含浸塗料)といって、床材表面に保護膜を形成するものではなく、床材に吸収されることで過度の乾燥や水分の吸収を軽減するものです。シートや突板に塗布しても、表面がベタつき、かえって汚れやすくなります。
塗るのが難しい塗料タイプ
床用ニスなどの油性塗料や色のついたカラーコーティング剤は未経験者は避けたほうが無難です。
油性塗料は上手に仕上げると床保護効果の高い塗膜を形成しますが、油性は特有の揮発臭がありますし、一般的に粘度が高くて均一にムラなく塗布することが難しいです。油性塗料は剥がすことができませんし、衣類や他の場所に飛び散った塗料を落とすのにも苦労します。
カラーコーティング剤はフローリングが色褪せてくると使用したくなりますが、色の濃淡が発生します。塗装で重なったところが濃くなったり、床の消耗している部分が液剤をより多く吸収して濃くなります。
レビューや素人意見でコーティング剤を選ぶ
商品レビューや専門家でない方の意見は参考程度にとどめましょう。当社で実際にあったケースで、レビューの高評価をみて購入したコーティング剤が自分のフローリングに合っていないものだったり、不動産会社の担当者の意見を鵜呑みにして間違ったコーティング剤を使用してしまった、などがあります。
マイホームのフローリングを自分でキレイで効果的なコーティングをするには、ぜひ、当記事を最後まで読んでください。
口コミや体験談でフロアコーティングを失敗しないための記事はこちら
業者施工の特徴とメリット

業者施工の良い点について紹介します。
専用機材と下地処理による仕上がりの違い
床材とコーティング剤が安定的に密着するよう、適切な下地処理を行うことが重要です。基本的にはクリーニングですが、場合によっては軽い研磨が必要なこともあります。業者ならポリッシャーやサンディングマシンを利用することもあります。下地を最適化して塗装することで、仕上がりには数段の差が生じます。
保証・耐久性・長期コストの優位性
業者施工では、使用するコーティング剤の性能や施工技術の違いにより、より長期的な耐久性があります。頻繁に再コーティングしなくてもよりので長期的には経済的なメリットもあります。また、業者施工では通常、10年~20年といった不良施工に対する手直し保証が備わりますので、万が一の状況にも安心です。
当社の施工実績とサポート体制
コーティングの施工では、業者でも不良施工はゼロではありません。家具の塗装とは異なり、住宅の床面積は広いため毛髪などの異物が混入したり、空気の循環のよくない一部のエリアで硬化不良がおこることもあります。また、入居直前の施工では、その後の家具搬入時に塗膜に傷をつけてしまうこともあります。
当社では、いずれのケースでも無償で迅速に手直しを行うサポート体制があります。不良施工に対する無償保証は10年間ですが、コーティングに関するお客様支援は永久に続きますので、ご要望や問題点などは遠慮なくご相談ください。
DIYと業者施工の比較表
ここでは、業者施工と比較検証されやすい、「ガラスコーティング」と「水性ウレタンコーティング」について表形式で比較します。
ガラスコーティングのDIYと業者施工を比較
| 項目 | DIY | 業者施工 |
|---|---|---|
| 初期費用(施工面積:30㎡) | 3.6~10万円 | 12~20万円 |
| 仕上がり(見た目) | 良い | かなり良い |
| 耐久性 | 5~10年 | 15~20年 |
| 不具合の補修 | 難しい | 依頼可能 |
| 施工保証 | なし | あり |
ガラスコーティング剤は市販でも高額なため初期費用はDIYでも安くありません。上手に塗れた場合はあまり仕上がりに差が出ませんが、材料の品質や塗装技術により業者施工の方が長持ちします。ガラスコーティングは塗膜物性等により一般ユーザーによる部分補修は困難です。業者なら依頼することにより無償もしくは有償で補修可能です。また、業者なら施工不良に対しての無償手直し保証があるのが一般的です。
水性ウレタンのDIYと業者施工を比較
| 項目 | DIY | 業者施工 |
|---|---|---|
| 初期費用(施工面積:30㎡) | 1~2万円 | 10~15万円 |
| 仕上がり(見た目) | 良い | かなり良い |
| 耐久性 | 1~3年 | 10~15年 |
| 不具合の補修 | 可能 | 依頼可能 |
| 施工保証 | なし | あり |
水性ウレタンは一般ユーザー向けのものと、業者が使用するものとの性能差が大きいです。フロアコーティング業者が使用するものは近年、環境配慮型として開発された、従来の油性ウレタンと変わらない強度のある水性ウレタンへとシフトされています。耐久性にはかなりの差が生じます。
毛髪の混入などの手直しは、水性ウレタンではやり方を学べば可能だと思います。業者なら依頼することにより無償もしくは有償で補修可能です。また、業者なら施工不良に対しての無償手直し保証があるのが一般的です。
こんな方には業者施工がおすすめ

- 長期的に張替えコストを抑えたい方
- ペット・小さなお子様がいて傷や汚れが気になる方
- 入居中で手間をかけたくない方
- ワックス剥がしが必要な方
- 広い面積にコーティングしたい方
- より完成度の高い施工を求める方
上記にあてはまる方は業者によるフロアコーティングをご検討ください。床を長期に保護する効果は、経験を積んだ職人の手による業者施工は費用に相当する価値があります。
また、床面積の広さ、入居中における家具移動の手間、ワックス剥がしの大変さなどは過小評価すべきではないです。経験からいっても、家具移動やワックス剥がしをともなうコーティングは工程にも工夫が必要になりますので美しい仕上がりを完成させるハードルが一段と高くなります。
フロアコーティングの業者選びはこちらの記事を参考にしていください
まとめ|目的に合った方法を選ぶ
DIYを検討する際の注意点は、以下の3つに集約されます。
- 床材種類にあったコーティング剤を選ぶこと
- 使用するコーティング剤のリスクを考慮すること
- 事前にマニュアルをよく読み、道具を揃え用意周到で臨むこと
また、ポジショントークになりますが、業者施工も長期的な視点ではメリットが大きいと思います。信頼のおけるフロアコーティング専門業者なら床材種類やユーザーの世帯構成・ライフスタイルに適したコーティング種類を提案してくれます。もちろん施工は専門の経験豊富で技術にある職人が手掛けます。初期費用はかかりますが、長くマイホームを良い状態に維持するには非常に有効な手段です。万が一の施工不良についても保証があるのは安心です。
新築や中古の物件を購入した方、すでにお住まいの方も、フロアコーティングに興味をお持ちなら当社の「スマホで簡単見積り」を、ぜひ、ご利用ください。間取り図をスマホで撮影し、見積りフォームを入力して送信するだけで見積書が届きます。金額を見てから、DIYで行うか検討されるのもよいです。ご相談やご質問も歓迎します。「見積りを依頼したからといって注文しなくては」と思う必要はまったくありません。お気軽にどうぞ!
フロアコーティングの基本から選び方・相場までまとめた
フロアコーティング総合ガイドもご覧ください。