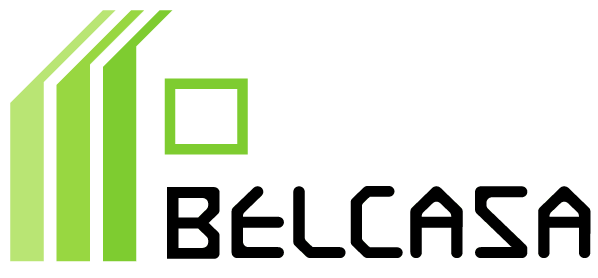最近ではDIYフロアコーティングにトライされる方も増えているようです。そこで本記事では、自分で実践される人向けに、作業手順や注意点を専門家視点から解説します。
当社には、フロアコーティングを自己流で塗ってみたけど上手くいかず、手直しを依頼される方がときどきいます。プロ並みに美しく仕上げる重要ポイントは、下地処理、道具、塗り方、作業環境などがあります。失敗をすると取り返しのつかないことにもなりかねませんので、リスクについてもお話します。
安易に始めるのはトラブルの元になります、フロアコーティングをDIYで実践したい方は、先ず本記事をご覧ください。
フロアコーティングをDIYで行うことは可能?
未経験者であっても自分でフロアコーティングを行うことは可能です。自分の家をコーティングした経験のある「先輩」として、詳しくDIYの失敗しない方法と注意点を解説します。
コーティング剤・塗装道具などの準備
ホームセンターや通販サイトなどで、すべて購入することができます。塗装に使用する、モップや刷毛は塗料に応じて選びましょう。たいていは取り扱い方法に推奨の塗装道具が記されています・
- コーティング剤:簡易的なモノから、本格的なプロが使用するものまであります
- 塗布道具:刷毛、ハンディコーター、モップなど塗料に合うものをチョイス
- トレイ:コーティング剤を入れる器
- タオル:複数枚を用意するよいでしょう
- バケツ:クリーニングに使用
- クリーナー:中性洗剤(台所用で代行可能)
- マスキングテープ:塗らないところに貼ります
- 粘着ローラー:あると便利。塗装直前の使用で異物混入が防げます
市販のDIY用コーティング剤の種類
現在、ホームセンターやECサイトでは多種多様なコーティング剤が入手可能です。大手通販サイトの売れ筋商品には以下のものがあります。カッコ内は代表的な製品の現在価格です。
- 水性ウレタン系:滑り防止性や抗菌性のあるものまで。(1L/3,960円)
- ガラスコーティング剤:傷防止性や子供の落書き対策。(1L/39,800円※施工キット一式付属)
- 自然塗料系:蜜蝋ワックス・植物性オイルなどが主成分。(120ml・2本/1,990円)
- スプレータイプ:艶出し・撥水にガラス成分が含まれるものも。(500ml/2,999円)
- 床用ニス:油性ウレタン床用ニス、つやあり・高耐久。(0.7L/2,092円)
DIYコーティングの標準的な工程
コーティング剤により多少違いがありますが、標準的には作業の流れは以下の通りです。
家具等を移動し施工範囲に何もない状態にします。
掃除機で除塵し、洗剤で希釈したクリーナー液で拭いてから水拭きする。
マスキングテープを巾木や塗らないエリアとの境界に貼る。
床面の乾燥と清掃状況を確認してから塗装する。
窓を開け換気する。塗料の使用方法に記載された時間を守ること。
乾燥を確認したら、家具を戻し完了です。
DIY向けコーティング剤の種類と選び方

インターネットを検索すると、業者向けの塗料まで一部には購入可能ですが、そこにはリスクもあります。知った上で購入するのなら自己責任ですが、中には「一般向け」というトーンで、プロでも、ある程度以上の経験がないと難しい油性塗料が売られていることもあります。知らないうちにリスクの高いコーティング剤を選ぶことのないよう注意ください。
また、床材との適合性も重要です。合わない組合せでは早期に剥がれてしまったり、汚れの原因になることもあります。
塗料タイプごとのリスク
| 塗料タイプ | 特徴 | DIYでの主なリスク |
|---|---|---|
| 水性ウレタン | 施工が比較的簡単。失敗しても剥がしやすい。(高密着タイプもある) | 塗りムラ。下地処理不足による剥がれ |
| 油性ウレタン | 高い光沢、耐久性 | 強い揮発臭(VOC)・塗装技術を要する・失敗時の補修がほぼ不可能 |
| シリコン | 滑り防止性・耐久性 | 下地処理不足による剥がれ・失敗時の補修が困難 |
| ガラス | 高硬度・高耐久 | 不均一塗装による塗膜形成不良。失敗時の補修が困難 |
| 自然塗料 | オイルや植物性ワックス。含浸性 | 不適合な床材への使用でベタベタした仕上がりに |
| カラー塗料全般 | 水性・油性の床用ニスを含む、色のついた塗料全て | 色の濃淡が発生する |
床材との適合性
| 床材 | 推奨される塗料タイプ | 注意点 |
|---|---|---|
| シートフローリング | 水性ウレタン(高密着タイプ)・ガラス | 厚塗りは剥がれの原因になる。 |
| 突板(複合)フローリング | 水性ウレタン・ガラス | 消耗している床は柔軟性のある水性ウレタンがベター。 |
| 挽板(複合)フローリング | 水性ウレタン・ガラス | 光沢値の高い床は塗り筋に注意。 |
| 無垢フローリング(素地仕上げ) | 自然塗料 | 吸水性が高いため他塗料はムラになりやすい。 |
| 無垢フローリング(オイル仕上げ) | 自然塗料 | 他塗料は密着不足になる可能性が高い。 |
| 無垢フローリング(造膜仕上げ) | 水性ウレタン・ガラス | 塗膜タイプにより性質が異なる。少面積で密着テストを実施すること |
自分の床材種類がわからない場合は、不動産会社や住宅メーカーの担当者に聞くとよいでしょう。また、床材との適合性には例外も考えられますので、大きい範囲を塗り始める前に、手のひら程度の小面積を塗装して乾燥後に剥がれないかチェックする「密着テスト」の実施をおすすめします。
塗るのが難しい塗料タイプ
床用ニスなどの油性塗料や色のついたカラーコーティング剤は未経験者は避けたほうが無難です。
油性塗料は上手に仕上げると床保護効果の高い塗膜を形成しますが、油性は特有の揮発臭がありますし、一般的に粘度が高くて均一にムラなく塗布することが難しいです。油性塗料は剥がすことができませんし、衣類や他の場所に飛び散った塗料を落とすのにも苦労します。
カラーコーティング剤はフローリングが色褪せてくると使用したくなりますが、色の濃淡が発生します。塗装で重なったところが濃くなったり、床の消耗している部分が液剤をより多く吸収して濃くなります。
【ご注意!】レビューや素人意見でコーティング剤を選ぶ
商品レビューや専門家でない方の意見は参考程度にとどめましょう。その商品が素晴らしくても自分の家の床に合うかどうかはわかりません。また、人それぞれ塗装の習熟度が違いますので、初心者の場合は、より慎重に判断した方がよいです。
DIYフロアコーティングのポイント

フロアコーティングはフローリングの表面に保護膜を形成する施工です。ある程度均一に塗らないと、ムラになったり、きれいな塗膜が形成しません。また、事前の清掃が不十分でゴミやホコリ、脂溶性の汚れが付着していると床と塗膜が密着せず、剥がれてくることもありますので以下のポイントに注意して作業しましょう。
- 塗装道具・コーティング剤にはこだわる
- 事前清掃ではしっかりとゴミを取り除く
- 塗る時は窓を閉める。塗布後に開ける
- モップ捌きは一連の動きでスムーズに(途中で止めない)
- 気温15~25℃・湿度50~70%の穏やかに晴れ渡った日に塗るべし!
塗装道具・塗料について
自分でフロアコーティングしたけれども上手くいかなった人の中には、塗装道具が貧弱だったということがります。床を清掃するフローリングワイパーのような口径の細い接手タイプのものだと、力がうまく伝わらないこともあります。塗る道具は、多少の出費にはなりますが品質の高い製品を選びましょう。
塗り方と事前の清掃についを
塗布作業の前にしっかりとクリーニングを行い、ゴミや埃などを取り除いておかないと塗膜の中に封じ込めてしまうことになります。床面だけではなく、テーブルの上のゴミなども作業中に舞い降りてくることがありますので気を付けましょう。
塗装は、一般の方が想像する以上に早く固まりはじめますので、モップでの塗布作業の途中で動きを止めてしまうだけで止め跡ができることもあります。一連の流れで、塗装道具の幅の4分の1ほど重ねながら、一筆書きのように動かしましょう。
間違えがちな換気方法
コーティング完了後に換気するのは推奨しますが、塗装中は直接風が床面に当たらないようにしてください。基本的にはエアコンは一時的に切ってください。窓も高い位置にあるものは開けておいてよいですが、掃き出し窓は必ず閉めましょう。
風が塗布した直後の塗膜に当たると瞬時に表面だけが乾きます、乾いた部分は折り返しで塗装が重なったときに内部で剥がれてしまうのです。塗り筋や塗りムラの原因になります。
最適な条件のときに塗ればよい
気温が高すぎても、低すぎてもコーティング施工の難易度が上がります。フロアコーティングの施工に最適な環境は、気温20℃前後、湿度60%前後です。気温が5℃を下回ると塗膜の硬化乾燥が極めて遅くなり、その間に、埃などが舞い降りてざらついた仕上がりになることがあります。気温が30℃以上に上昇すると、今度は極端に硬化乾燥が早くなり塗り筋や塗りムラが出やすくなります。湿度が極端に高いときも、塗料種類によっては塗膜形成に問題が生じることがあります。
プロならどんな条件でも一定以上の仕上がりが求められますが、一般の方なら、条件の悪い日はパスして良い条件のときに作業するのがよいでしょう。
業者施工の特徴とメリット

業者施工の良い点について紹介します。
専用機材と下地処理による仕上がりの違い
床材とコーティング剤が安定的に密着するよう、適切な下地処理を行うことが重要です。基本的にはクリーニングですが、場合によっては軽い研磨が必要なこともあります。業者ならポリッシャーやサンディングマシンを利用することもあります。下地を最適化して塗装することで、仕上がりには数段の差が生じます。
保証・耐久性・長期コストの優位性
業者施工では、使用するコーティング剤の性能や施工技術の違いにより、より長期的な耐久性があります。頻繁に再コーティングしなくてもよりので長期的には経済的なメリットもあります。また、業者施工では通常、10年~20年といった不良施工に対する手直し保証が備わりますので、万が一の状況にも安心です。
当社の施工実績とサポート体制
コーティングの施工では、業者でも不良施工はゼロではありません。家具の塗装とは異なり、住宅の床面積は広いため毛髪などの異物が混入したり、空気の循環のよくない一部のエリアで硬化不良がおこることもあります。また、入居直前の施工では、その後の家具搬入時に塗膜に傷をつけてしまうこともあります。
当社では、いずれのケースでも無償で迅速に手直しを行うサポート体制があります。不良施工に対する無償保証は10年間ですが、コーティングに関するお客様支援は永久に続きますので、ご要望や問題点などは遠慮なくご相談ください。
DIYと業者施工の比較表
ここでは、業者施工と比較検証されやすい、「ガラスコーティング」と「水性ウレタンコーティング」について表形式で比較します。
ガラスコーティングのDIYと業者施工を比較
| 項目 | DIY | 業者施工 |
|---|---|---|
| 初期費用(施工面積:30㎡) | 3.6~10万円 | 12~20万円 |
| 仕上がり(見た目) | 良い | かなり良い |
| 耐久性 | 5~10年 | 15~20年 |
| 不具合の補修 | 難しい | 依頼可能 |
| 施工保証 | なし | あり |
ガラスコーティング剤は市販でも高額なため初期費用はDIYでも安くありません。上手に塗れた場合はあまり仕上がりに差が出ませんが、材料の品質や塗装技術により業者施工の方が長持ちします。ガラスコーティングは塗膜物性等により一般ユーザーによる部分補修は困難です。業者なら依頼することにより無償もしくは有償で補修可能です。また、業者なら施工不良に対しての無償手直し保証があるのが一般的です。
水性ウレタンのDIYと業者施工を比較
| 項目 | DIY | 業者施工 |
|---|---|---|
| 初期費用(施工面積:30㎡) | 1~2万円 | 10~15万円 |
| 仕上がり(見た目) | 良い | かなり良い |
| 耐久性 | 1~3年 | 10~15年 |
| 不具合の補修 | 可能 | 依頼可能 |
| 施工保証 | なし | あり |
水性ウレタンは一般ユーザー向けのものと、業者が使用するものとの性能差が大きいです。フロアコーティング業者が使用するものは近年、環境配慮型として開発された、従来の油性ウレタンと変わらない強度のある水性ウレタンへとシフトされています。耐久性にはかなりの差が生じます。
毛髪の混入などの手直しは、水性ウレタンではやり方を学べば可能だと思います。業者なら依頼することにより無償もしくは有償で補修可能です。また、業者なら施工不良に対しての無償手直し保証があるのが一般的です。
こんな方には業者施工がおすすめ
下記にあてはまる方は、業者によるフロアコーティングをご検討ください。床を長期に保護する効果は、経験を積んだ職人の手による業者施工は費用に相当する価値があります。
- 長期的に張替えコストを抑えたい方
- ペット・小さなお子様がいて傷や汚れが気になる方
- 入居中で手間をかけたくない方
- ワックス剥がしが必要な方
- 広い面積にコーティングしたい方
- より完成度の高い施工を求める方
また、床面積の広さ、入居中における家具移動の手間、ワックス剥がしの大変さなどは過小評価すべきではないです。経験からいっても、家具移動やワックス剥がしをともなうコーティングは工程にも工夫が必要になりますので美しい仕上がりを完成させるハードルが一段と高くなります。
まとめ|DIYかプロかを決定するポイント
DIYを検討する際の注意点は、以下の3つに集約されます。
- 床材種類にあったコーティング剤を選ぶこと
- 使用するコーティング剤のリスクを考慮すること
- 事前にマニュアルをよく読み、道具を揃え用意周到で臨むこと
手前みそになりますが、業者施工も長期的な視点ではメリットが大きいと思います。ベルカーサなら一人一人のお客様の状況に最適なフロアコーティングをご提案し、専門の職人が丁寧に仕上げます。
家具の移動があったり、床のクリーニングが必要であっても、まったく問題ありません。マイホームの床をキレイに保つお手伝いをする仕事ですから、フローリングの悩みは何でも気軽にご相談ください。